こんな講座ありました(学ぼう!飛鳥の地蔵盆2025)
- 更新日:2025年9月10日
- ID:15378
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
学ぼう!飛鳥の地蔵盆2025<飛鳥公民館:2025年7月19日(土)>
この講座は、地域に伝わる伝統行事「地蔵盆」の意味や背景を、大学生と一緒に参加者同士で楽しく学ぶことを目的とし、今回で7回目の開催となりました。
奈良教育大学教育学部「地域文化論」受講の学生たちが講師・進行役となり、各町のお地蔵さまや地蔵盆についてのお話、地蔵巡り、My地蔵作りなど、盛りだくさんの内容でわかりやすく説明してくれました。
講座の様子
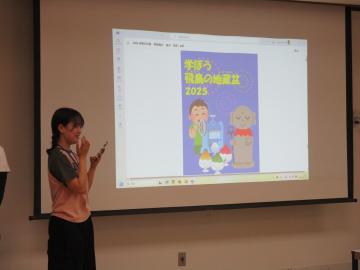
講座の始めに大学生から、この後巡る各町にまつられているお地蔵さまの特徴や由来について、丁寧な説明がありました。お地蔵さまの歴史や地域の方々との関わりを知ることで、参加者の皆さんは地蔵巡りへの期待を膨らませていました。
続いて、地蔵盆の由来や意味、地域ごとの行事の様子についても紹介。写真やエピソードを交えたわかりやすいお話に、昔の地蔵盆を懐かしく思い出された保護者の方もいらしたのではないでしょうか。

地域に伝わる伝統行事のひとつ「数珠繰り」を体験するため、興善寺を訪れました。お寺の本堂に集まり、大きな数珠を囲んで、ご住職のお話を聞いたあと、みんなで数珠を繰って手を合わせました。
子どもたちも保護者も、静かな空間の中で一人ひとり願いを込めて数珠にふれ、心が落ち着くひとときを過ごしました。

続いて「川中地蔵」を訪れました。現在は道路沿いに祀られていますが、もともとはこの辺りを東西に流れていた川沿いにおられたと伝えられています。お地蔵さまを大切に守ってこられた管理者の方から「子どもの頃は、裏の畑にいらっしゃった。その後、もっと多くの人が手を合わせられるようにと、今の場所に移した」とのお話を伺った大学生が参加者に説明してくれました。
変わりゆく風景のなかで、地域の人々の暮らしと共に場所を移しながら守られてきたお地蔵さま。その背景にある想いや祈りにふれる貴重な機会となりました。

中通町で大切に守られているお地蔵さまにもお参りしました。このお地蔵さまは、町内の各家庭を毎月23日に順番に回って祀られており、地域の人々の間で長年にわたり受け継がれてきた信仰のかたちです。このような文化が残る地域は珍しいそうで、大学生の説明に子どもたちは、真剣な表情で耳を傾けていました。
訪問の際には判読できなかった木箱に書かれていた文字ですが、後日、専門家の方に確認していただいたところ、「寛政二年」と記されていることがわかったそうです。江戸時代後期にあたる年代で、地域に伝わるお地蔵さまの歴史の深さを改めて感じる発見となりました。

地蔵町の裏路地にある集会所では、地域の方々に大切に守られているお地蔵さまに出会いました。細い路地の奥にひっそりとたたずむその姿に、子どもたちは「こんなところにお地蔵さまがいるなんて!」と驚いた様子。
集会所では、地域の方が丁寧にお花を手向け、清掃やお世話を続けておられることを知り、地域の人々の温かさや思いにふれることができました。
昔からこの場所で地域の安寧や子どもたちの成長を見守ってきたお地蔵さま。その存在は、静かな路地の中でもしっかりと、地域の心の拠り所となっていました。

笠屋町にあるお堂に安置された「鎧地蔵」を訪ねました。鎧を身にまとった珍しいお姿のお地蔵さまで、普段は防犯上の理由からお堂の扉が閉められていますが、毎年7月23日の地蔵盆の日だけ特別に公開されているそうです。
地域の方を取材した大学生によると、地蔵盆の日には他府県からも見学に来られる方がいるほどで、地域の誇りとして大切に守られてきたことが伝わってきました。
歴史と信仰が息づくこの場所で、子どもたちも地域文化の豊かさと大切さを感じてくれていたら嬉しいです。

幸町のお地蔵さま「鉈枝口地蔵尊」が安置されているお堂を訪ねました。ちょうどこの日は幸町の地蔵盆で、お地蔵さまの前では子どもたちが喜ぶビンゴゲームなどの催しが行われていると事前に聞いておりました。
私たちが到着したときには催しはすでに終わっており、子どもたちのにぎやかな声は聞けませんでしたが、町内の方々が片付けの準備のため集まっておられ、本日の様子や行事についてお話を伺うことができました。
お地蔵さまを中心に、世代を超えた交流の場をつくっておられる町内の皆さんの姿に、私たちも心が温かくなりました。地域で大切に受け継がれてきた行事が、今も子どもたちの笑顔とともに息づいていることを感じられた、心に残るひとときとなりました。

大学生が用意してくれたお地蔵さまのイラストに、子どもたちが自由に色を塗って「My地蔵」を作りました。色鉛筆などを使って、思い思いの飾り付けを楽しみながら、世界に一つだけの作品が次々と完成していきました。
子どもたちは作品に込めた思いやこだわりを嬉しそうに教えてくれました。
大学生のお兄さん・お姉さんと交流しながら、地蔵盆の意味を感じ、自分なりに表現する、そんな心温まるひとときとなりました。
講座の最後には、飛鳥地区自治連合会長から子どもたちへ温かいお言葉をいただきました。さらに、飛鳥地区自治連合会より、お菓子のプレゼントもいただき、子どもたちはとても嬉しそうな表情を見せていました。
子どもたちにとって、心に残る嬉しいお土産になりました。自治連合会の皆さま、素敵なプレゼントを本当にありがとうございました。
参加者の声
参加者の子どもたちや付き添いの保護者からは、
「お菓子もらえてうれしかった」
「さまざまなお地蔵さまが見れて良かった」
「他の家に回されていくお地蔵さんが驚きで面白かった」
「なかなか見れないお地蔵さんを案内してもらい貴重な体験となりました。地域の文化になっていて、各町内の方々とも交流できて嬉しかったし、奈良をまた一歩詳しく知ることができました。大学生さんも親切で、子どもに気さくに接していただきありがとうございました。スタンプラリー、たくさんのお菓子、町歩き、My地蔵、子ども達が楽しめる工夫があり、かき氷も美味しかったです。本当にありがとうございました。」
などの声が聞かれ、世代を超えて地域の文化を共有する貴重な時間となりました。
講座を終えて
今後も、地域の風習や歴史を次世代に伝えていく活動を、皆さんと一緒に続けてまいりたいと思います。
ご参加いただいた皆さま、また運営にご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。
補足:講座当日に配布した大学生による手作りのお地蔵さまに関する冊子については、奈良教育大学のホームページにて近日中に公開される予定です。公開されましたら、ぜひご覧ください。
お問合せ
飛鳥公民館
住所: 〒630-8306 奈良市紀寺町984番地
電話: 0742-23-2804
ファックス: 0742-23-2804
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
