こんな講座ありました(シニアからの教養講座)
- 更新日:2014年3月7日
- ID:4590
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
シニアからの教養講座<平城東公民館:2013年10月22日(火)~2014年1月28日(火)全4回>
現在、朱雀・左京・佐保台地域の65歳以上の人口は、全体の22%を占め、いわゆる「超高齢社会」となっています。
それと同時に、核家族化が進み、高齢者夫婦世帯や独居老人の数も増加し、孤独死は社会問題となっています。
そこで、少しでも外に出て、同じ地域に住む者同士で学習することで顔見知りになり、共に助け合える仲間づくりのきっかけをつくることを目的に、健康・文化・ライフスタイルなどをテーマにした学習を企画しました。
第1回目:2013年10月22日(火)「パワースポットを歩く」in春日大社
第2回目:2013年11月26日(火)「年金生活の節約術」
第3回目:2013年12月17日(火)「基礎からまなぶ風土記1300年」
第4回目:2014年 1月28日(火)「豊かなセカンドライフを過ごすために」
以上、4回にわたり学習しました。
第1回:2013年10月22日(火) 「パワースポットを歩く」in春日大社

第1回目は、古都奈良の世界遺産の1つである春日大社を案内いただき、たくさんのパワースポットを巡りました。
まずは、春日大社二ノ鳥居前に集合し、開講式をしてから、案内してくださった春日大社禰宜より、春日大社の概要説明を聞いて、いざ出発です!

二ノ鳥居を入ってすぐにある、燈籠の説明をしていただきました。
禰宜が指されている燈籠の下の部分には、鹿の絵が巻き付いていました。

ずらりと並んだ燈籠は圧巻です!
春日大社は、燈籠の数が日本一多く、石燈籠2,000、釣燈籠1,000あるそうです。

春日大社には、日本で唯一のご夫婦の大國様をお祀りした「夫婦大國社」があるのをご存じでしたか?
「良縁や商売繁昌を願って叶えられぬことなし」と伝えられているそうです。

清めの水で手と口を清めて、いよいよ本殿に入ります。

この日は特別に禰宜のはからいで、特別参拝をしていただきました。
受講者の皆さんも、「突然のことでしたがとても嬉しく思います。」とおっしゃっていました。
ここには載せきれないくらい詳しく、春日大社をご案内いただきました。
身近にあるけれど、春日大社には世界遺産の迫力がありました。
古都奈良の世界遺産を大切に守っていくことを、私たちはもちろん、その後に続く者に継承していかなければと、改めて感じました。
第2回:2013年11月26日(火) 「年金生活の節約術」

第2回目は、「年金生活の節約術」と題して、ファイナンシャルプランナーの方にご講演いただきました。
やはり、「シニアからの教養講座」だけあって、受講者の大半の方が年金で生活をされています。
先生は、「年金制度を正しく理解し認識するのは、ファイナンシャルプランナーでさえ勉強を重ねなければ難しい。」とおっしゃっていました。

また、この講座の前日に、遺族基礎年金の法改正がされました。
先生は、このことについても追加でご説明くださいました。

2005年~2013年までの統計で、高齢夫婦世帯の生活費の不足額は年々増加傾向にあるとのこと。
2013年度では、51,674円の「赤字」になっているそうです。
つまりこの赤字は、それまでに積み立てた預金等から補填されるわけなのですが・・・来年消費税が引き上げられたら・・・もっと赤字が増えてしまいますよね。

先生は、「公的年金だけではカバーできない生活資金の確保、リフォームや趣味等を実現する資金等、これから失っては困るお金や、絶対に必要になるお金をもう一度見直して、いつまでもお元気で。」と結ばれました。
第3回:2013年12月17日(火) 「基礎から学ぶ風土記1300年」

「基礎から学ぶ風土記1300年」と題して、奈良県立万葉文化館から講師を招いて、ご講演いただきました。
今年は「風土記1300年」にあたることに因んで、風土記への教養を深めてもらえたらと、組み込みました。
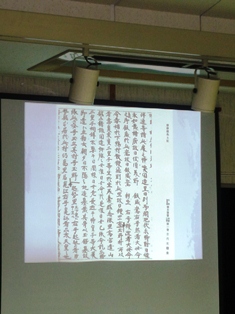
「風土記」とは、国や地域ごとの風土・産物・文化などを記した地誌のことで、平安時代や江戸時代につくられたものは「風土記」と呼び、古代につくられたものは区別して「古風土記」と分類されるということです。
現在唯一の完本として残っているのは、「出雲国風土記」だそうです。
あとは、一部が欠けていたり省略されたりしていて、完全には残っていないということでした。

因みに、奈良県(大和国)の風土記は古代の風土記ではないと考えられていて、逸文として少しだけ残っているそうです。
逸文・・・失われた書物が別の書物に引用されて残った文章
最後に、「播磨国風土記」を声に出して読んでみました。
風土記は漢文で書かれているので難しいですが、先生にレクチャーいただいて読み上げました。
「播磨国風土記」には、奈良の大和三山の歌に関係する記述があるということで、その部分を読んでみました。
第4回:2014年1月28日(火) 「豊かなセカンドライフを過ごすために」

最終回は、充実したセカンドライフを過ごすために、頻繁に改正される税法の解説から、有効な資産活用などを学びました。

講師が今まで税相談を数多く受けてこられた中から、事例をいくつか挙げ、面白く解説してくださり、難しいと言われている税金の話を、興味深く、時に笑いを交えながら聞くことができました。
参加者の声
- 大変すばらしかった。大いに参考になった。
- なじみにくい税の話をわかりやすく、おもしろく講義いただきました。
- 初めて参加しました。機会があれば次回も参加したいと思います。
- 会場ばかりでなく、屋外に出て奈良の歴史を学ぶ部分があって、大変よかった。
- 知らないことも多く、興味深く聞かせていただいた。
お問合せ
平城東公民館
住所: 〒631-0806 奈良市朱雀六丁目9番地の1
電話: 0742-71-9677
ファックス: 0742-71-9677
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
