こんな講座ありました(くらしの文章教室~想いを書くこと、綴ること~)
- 更新日:2024年3月5日
- ID:13692
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
くらしの文章教室~想いを書くこと、綴ること~<登美ヶ丘南公民館:2023年6月27日(火)・7月25日(火)・9月26日(火)全3回>
この講座は、3年前の新型コロナウイルスの蔓延等で公民館が臨時休館となり、その間の日々の些細な出来事や、ふとした発見、心の動きなどを文に書きとめたことなどを作文として募集し、それらを『登美南誌録』として綴ったことが始まりです。
その際に聞こえてきたのが、文章を苦手とする方の多さでした。
それに応えるため、フリーライターを講師に迎え、自分の気持ちや出来事などをうまく伝えるための文章を書くコツとして、「コト」「キモチ」「タネ」を基本に、日常のちょっとした出来事を文章にして綴ることを学ぶ講座を開催しました。
2021年に始まった講座も今年で3回目を迎え、人気講座となりました。
第1回:6月27日(火) 文章のいろはちょっと書いてみる
まずは、書きたいコト、書きたいキモチを自身に問いかけます。
コトを読ませるための味付け、それをタネと呼びます。

講師は、フリーライターの新井忍さんです。
冒頭、新井さんは参加者にあなたが書きたいコト、書きたいキモチを問いかけました。

皆さん、緊張しながらも文章の解説や語りに引き込まれていきます。
テキストには、2023年度に館から発刊した『登美南誌録第三巻』と、新井さんが書いた例文をもとに、文章の基本を学んでいきます。
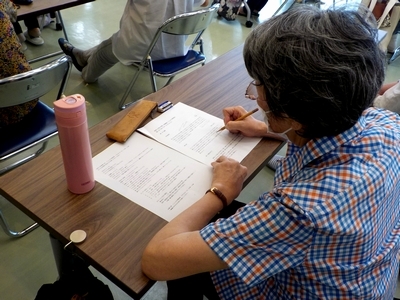
こうして一日目は、テクニックとして、センテンスの長さや、接続詞、語尾、タイトルなど、総合的に違和感のないように整えることを学びました。
最後に次回までに、200字程度の文章を書く宿題が出されました。
みなさん、宿題が出るとは思っておらず、びっくり!?
「えー、書けるかなあ」「この歳になって宿題をする事になるとは」など、戸惑いの声も。
「学生に戻った気分で頑張ります!」と意気込んでくださる方も!
さて、1か月後にどんな作品に出会えるのか楽しみです。
第2回:7月25日(火) “私のくらし”を綴ってみる
第2回が始まりました。
前回に出された宿題、200字程度の文章を事前に文集にしました。
この文集をテキストに学んでいきます。
どれも力作ばかりで、講義が楽しみです。

宿題が億劫だった人、楽しくて仕方のなかった人、皆さん一生懸命に考え、ユーモアたっぷりの文章が集まりました。
まずは新井さんが宿題の文章を朗読し、感想とアドバイスを述べたのちに作者へ質問をします。
「この時の気持ちはどうでしたか?」「季節はいつ頃ですか?」など具体的に。

新井さんからの質問に、作者の方が答えます。
「この時は晴れていて」とか、「自分が子どものころの話で」「妻とのやり取りの中で」など、人それぞれにシチュエーションが違えば時代背景も違う。
新井さんは、本人の想いを分かりやすく皆さんに伝えるためのアドバイスを一人一人丁寧に行っていきます。
先生の言葉は本当に優しく褒め上手!
文章を書くことに抵抗を感じなくなっていく新井マジックです!
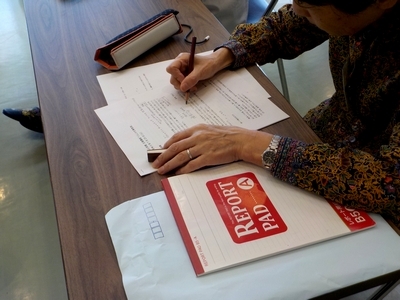
自分の文章にどんな講評をしてもらえるのか、他の人たちの作品にどのような視点や工夫、改善点があるのかを一緒に考え、今後の文章作りに活かす力を養いました。
自分の文章だけでなく、皆さんの文章の良い点や、気を付けるべきポイントなど、しっかりメモを取っていきます。
前回の200字の宿題に引き続き、今回も同じく200字の宿題です!
今回の皆さんの反応は前回と打って変わって、やる気モード。
自分の文章、他の人の文章が、新井さんのアドバイスによって見違える。
そんな光景を目の当たりにして、文章を書くことの楽しさにわくわくしているように見えました。
第3回:9月26日(火) 宿題のふりかえり
第3回も出された宿題の講評から始まりました。
前回は、宿題に対して自分が発表をすると思っていなかったので、うまく伝えられなかったとおっしゃる方も。
でも今回は違う!
皆さんそれぞれの想いをしっかり伝えてくださいました。
参加者の皆さんが真剣に聞いている姿がとても印象的でした。
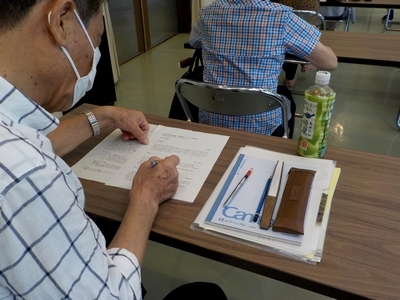
自分の文章への講評も、他の方の講評もしっかり聞き取ります。
他の方の文章も「くらしの文章教室」のオリジナルのテキストです。
参加者の声
参加された皆さんからの感想や、これからの意気込みなどお聞かせいただきました。
- 自分の文章は自分では推敲しにくいもの。先生のアドバイスが的確でした。
- 200字では表現のテクニックに苦労した。
- 3回の勉強で何かコツがわかったような気がします。学んだことを意識しながら書く楽しみを持ち続けたい。
- 毎回書いた文章に先生がどのようなコメントをされるのか、とても興味があった。
- 宿題もあり、充実した内容でした。
など、たくさんの声を聞かせていただきました。
講座を終えて
皆さん、今後の文章作りへの大きな抱負を語り、次回開催への期待を胸に帰られました。
「文章を書くことが苦手だから」「独自で書いているけど、書き方などはあるのか」など、参加者の想いはさまざまで、不安な気持ちで参加した方が多かったのですが、講座が終了する時には、「文章を書くことも、皆さんの作品を読み考えることも、とても楽しかったし勉強になった」という言葉に、先生も私たち職員も大変嬉しく思いました。
この講座をきっかけとし、これからも皆さんが日頃から文章に親しまれることを願っています。
講座の後に今回提出した文章を各々が修正して再編集した『登美南誌録 第四巻』を発刊しましたので、『登美南誌録』(初刊~三巻)とあわせて、ぜひご一読ください。
登美南誌録
登美南誌録 第二巻
登美南誌録 第三巻
登美南誌録 第四巻
お問合せ
登美ヶ丘南公民館
住所: 〒631-0013 奈良市中山町西二丁目921番地の1
電話: 0742-47-6375
ファックス: 0742-47-6375
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
